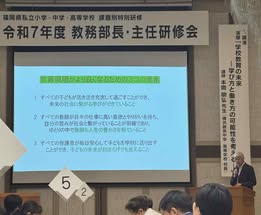2030年度からの学習指導要領の順次実施に向けて、順調に進めば2026年度中に答申が公表されます。そこを起点に2年ほどのスパンで教育課程を編成していくことになります。
本校は働き方改革で2年、カリキュラム改革で2年、学校改革を仕上げるまでに4年の月日を要しています。本校がカリキュラム改革に没入できたのは、働き方改革がすでに終わっていたゆえのことです。働き方改革は、時間外労働を減らすことが目的ではありません。新しい学校像の実現に向けた改革を進めるためには、どうしても先生方の時間に余白を作ることが不可欠だったのです。
負担が増える学校改革は必ず失敗します。改革は足し算でなく引き算でなければいけない。次期学習指導要領に向けた教育課程の編成は、柔軟化や弾力化など、各学校の裁量が大きく広がります。想定以上に時間や工数を要するはず。カリキュラム改革に着手するためには、その前段としての働き方改革にメドをつけることは不可欠なことです。
教育に終わりはありません。学校改革は自分の思い通りになんかならないかもしれないし、理不尽なこともたくさん生じるだろうと思います。でも、それは当たり前のことで、それを理由に、「その場にとどまる」のではなく、思い通りにならないからこそ、「一歩前に踏み出して壁を破る」ことに意味があるのではないかと思うのです。
学校はすべての生徒の幸せを探す場所です。それならば、学校は一人ひとりを支えるために、課題に蓋をすることなく、私たちが出来うる教育の可能性を探すべきだ。
こうした学校改革について、合間を見て各地に出かけながら、講演でお伝えをしています。今月は福岡県と兵庫県で講演をさせていただいたほか、名古屋市教育委員会と芦屋市教育委員会の方々が来校され、本校の学校改革について共有をさせていただきました。11月は兵庫県教育委員会と横浜市教育委員会のお招きで校長・副校長の方々に講演予定で、未来を先取りした教育について共有ができたらと考えています。